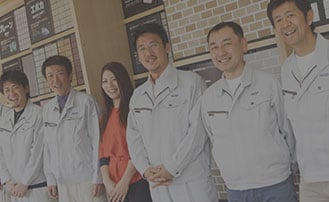鉄の不思議1 〜パレドⅢ〜
釉薬の秘密
日東オリジナルタイル パレドⅢ
No.PA-315
弊社商品の中でも、異彩の雰囲気を醸し出す質感のあるタイル。
お客様から、ご注文頂き、まさに色調調整をしている商品。
写真は、色チェックのためのテストピースです。
①は、サンプルピース(ねらい色)に対し、
②は今回生産した釉薬の発色状態を確認するためのピース。
写真では、①と②が、ほぼ同じ色に見えるテストピースも、
日光の下、肉眼で見るプロの判断は、当たり前のように再修正
いったい何が違うのか
それだけ厳しい目で見られている秘密を探ってみましょう。
ピース①が、若干黒味を帯びているのに対し、
ピース②は少し白く若干赤味も帯びている。
では、黒系の顔料を追加したら、もっと似るのでは
絵画の世界だと、そう考えがちだが、釉薬の世界はそんな単純ではない。
それは、色自体が自然界から生まれた発色だからである。
前回、東京駅で紹介したレンガの発色に関わる鉄。
実はこのシュールさに深く関係している。
このタイルの焼成とはは酸化のことを示す。
つまり、②のテストピースは、①よりも酸化がにぶいということ。
いわゆる中性化しているのである。
簡単に言えば、焼く具合が違うのである。
鉄はその焼き具合によって、見るからに赤くもなり黒くもなる。
調合によっては、水色(青磁)、結晶釉にもなる。
つまり、火の具合だけで様々な色の変化が生まれ、
何一つとして同じパターンが存在しない世界。
焼き具合に合わせ、釉薬成分を調整することは、
知識、経験はもちろん、発色を感じとるセンスがかなり重要になるである。
釉薬に関わる鉄の発色は、プロをも魅了する興味深いもの。
途方もない時間をかけて極めてゆく世界である。
次回もう少し詳しく、鉄の発色の不思議を、ご紹介出来たらと思っています。
おつきあいのほど、よろしくお願いします。
若尾 幸裕
iPhoneからの投稿
最後まで読んでいただきありがとうございます。
この記事は私が書きました!