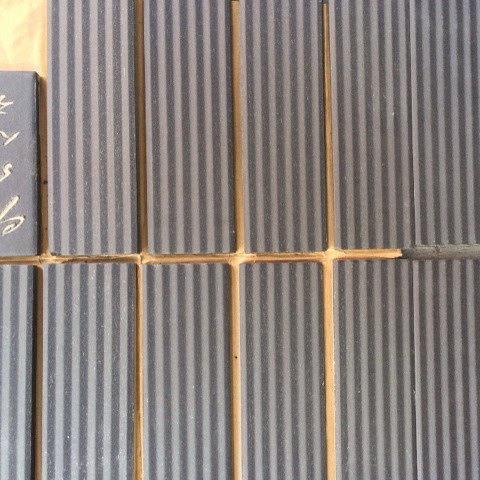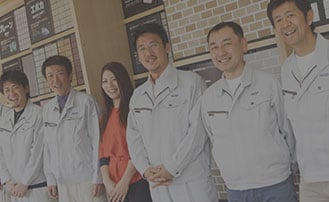釉薬の行方・・・パート①
釉薬の秘密
皆さん、ご無沙汰してます釉薬の秘密「くまちゃん」です
4月にちなんで 「桜」 ということで・・・

ジャーン釉薬で、夜桜の絵を描いてみましたなかなかでしょ
実は、ブログにご紹介されてますがhttp://ameblo.jp/swantile/entry-11817505639.html
4月から入る、新たな仲間新入社員歓迎っと言う意味もこめて、社内でお花見しました
この日は、私用の為、準備だけして帰らせてもらいましたが、このライトアップ私がやったんですよー
すなわちこれ絵じゃないんですよーエイプリルフールの4月にちなんで軽~いジョークでした
っとまぁ・・・おふざけがすぎましたねすいません・・・
っという事で、本題行きましょう
前回、釉薬が出来上がるまでご紹介させていただきました

さぁー出来たー早速、タイルを生産しましょう
とは、いかないんですねーここからが、釉薬の難しい所でもあり、楽しい所でもあるんですねー
まず、色の確認が必要の為、ピース試験をいれます
左の4列は、お客様から注文頂いた分の見本のタイルになります
右の1列は、出来上がった釉薬を、色の確認の為2ピース焼いた物です
どうですかわかりずらいですが、見本に比べ少し赤いですねっということは、この釉薬では色が違うため生産できません
ので、釉薬の色を修正したものを何点かいれます
なかなかいい色がありますねここで次の工程 「先発」 という工程に入ります
これはどんな工程かというと…大体15リットル~30リットル程の釉薬を使いごく少量実際に生産します
生産前に釉薬の色を、最終的に確認するための工程です
釉薬の修正試験を参考にして、いざ先発
出てきた「先発」を…
営業マンと釉薬担当者が確認しております
がっ釉薬担当者の眉間がしわしわ…
恐る恐る失礼すると…
奥に並べてあるタイルが先発なんですが…赤味が強いですね
この色では、お話にならないので、再度試験ピースいれて→先発という流れになります
釉薬は、自然な環境の中で作られるものなので ‘色を安定させて出す‘ という事が難しい物ですが、色がバシッと合った時はなんともたまんないですね
そんな、苦労を経て実際に建物として地図に残っていくんです
素敵な話ですよねだからこそ、釉薬は難しいですが、楽しいんです言う事聞いてくれない感じがたまらないです・・・
んっ言う事を聞いてくれない釉薬っ
そういえば、タイル業界では、そういう状態を 「あばれる」 なんていいまして・・・
っと言うことで、次回はこの「あばれる」について検証したいと思います
っとこの、赤味を帯びたタイルは無事生産にたどりつけたのでしょうか
どちらもお楽しみに~
くまちゃんでした
最後まで読んでいただきありがとうございます。
この記事は私が書きました!